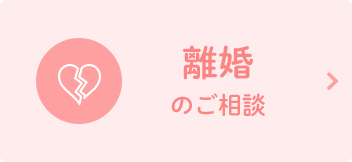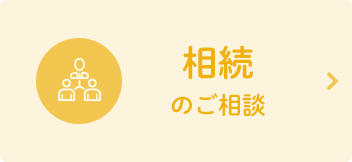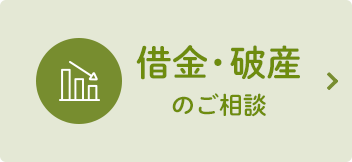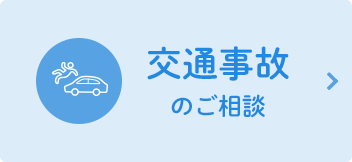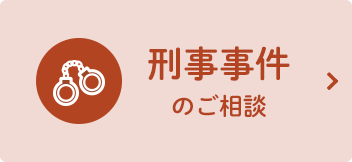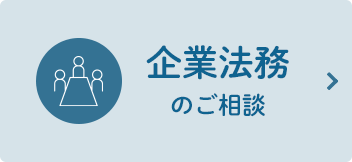保険会社から示談書が届いた【示談書にサインする前に確認すべき点は?】
交通事故に遭い、怪我の治療が一段落すると、多くの場合、加害者側の保険会社から「示談書」が送られてきます。
示談書とは、交通事故の損害賠償問題について、当事者間で合意した内容をまとめた契約書のようなものです。示談書にサインしてしまうと、原則として後から内容を変更することはできません。
しかし、示談書の複雑な内容を十分に理解しないまま、安易にサインをしてしまうケースは少なくありません。
そこで今回は、保険会社から示談書が届いた際に、なぜ慎重な対応が必要なのか、そして具体的にどのような点をチェックすべきかについて、詳しく解説していきます。
1 示談書とは何か
示談書とは、交通事故によって生じた損害(治療費、休業損害、慰謝料など)について、被害者と加害者や加害者側の保険会社が話し合い、その合意内容を書面にまとめたものです。
示談は、民法上の「和解契約」にあたり、一度成立すると、当事者双方を法的に拘束する力を持つことになります。
示談書には、通常、以下の項目が記載されています。
- 事故の概要:いつ、どこで、どのような事故が起きたか
- 示談金の総額:治療費、休業損害、慰謝料、物損などの合計額
- 内訳:それぞれの費目ごとの金額
- 清算条項:示談金を受け取ることで、これ以上、被害者が加害者に一切の請求をしないことを確認する条項
- 署名・押印欄:当事者の署名と押印
上記の項目の中では、清算条項が非常に重要です。清算条項がある示談書にサインするということは、この示談書に記載された内容で、今回の交通事故に関するすべての請求を終了させることを意味します。
後から「やはり損害額が足りなかった」「あの後、別の後遺症が出てきた」と主張しても、原則として追加の請求はできなくなります。
2 なぜ示談書にサインする前に確認が必要なのか
保険会社から送られてくる示談書は、あくまで自社の支払い基準に基づいて算出された内容が記載されており、必ずしも被害者が法的に受け取ることができる満額の賠償額とは限りません。
日本の損害賠償額には、主に以下の3つの算定基準があります。
- 自賠責基準:自動車損害賠償責任保険が定める最低限の補償額
- 任意保険基準:各保険会社が独自に定める社内基準。通常、自賠責基準よりは高額
- 弁護士基準(裁判基準):過去の裁判例に基づいて算出される基準。3つの基準の中で最も高額
保険会社が提示する示談金は、通常、任意保険基準で算出されています。しかし、弁護士が交渉にあたる場合や、裁判に発展した場合には、最も高額な弁護士基準が適用されることが多くなります。
つまり、被害者自身が交渉に臨むと、本来受け取れるはずの賠償金より低い金額で示談してしまうリスクが高いのです。
特に、後遺障害が残った場合や、重度の怪我を負った場合、示談金の差額は数百万円、場合によっては1000万円を超えることも珍しくありません。この差額を知らずにサインしてしまうことは、大きな損失につながることを意味するといえます。
3 示談書で確認すべき点
では、具体的に示談書のどの部分を注意深くチェックすべきでしょうか。
3-1 過失割合
示談書には、事故における当事者双方の過失割合が記載されています。たとえば、「被害者10:加害者90」といった具合です。
この過失割合は、示談金の額に直接影響します。被害者にも過失があるとされた場合、過失割合の分だけ受け取れる示談金が減額されるためです。
保険会社が提示する過失割合は、必ずしも客観的な事実に基づいているとは限りません。ドライブレコーダーの映像や、警察が作成した実況見分調書などを確認し、納得できる過失割合かどうかを慎重に判断する必要があります。
3-2 損害費目の漏れがないか
示談書に記載された損害費目が、すべて網羅されているかを確認することが必要です。具体的には、以下の項目について確認する必要があります。
3-2-1 治療費
健康保険を利用しなかった場合の自費診療分や、接骨院・整骨院の費用は含まれているか確認する必要があります。
3-2-2 休業損害
休んだ日数分、適切な金額で計算されているか、専業主婦(主夫)の休業損害や自営業者の減収分も含まれているかの確認が必要です。
3-2-3 入通院慰謝料
入通院した期間や日数に応じて、適切な金額で計算されているかという点が重要です。
3-2-4 後遺障害慰謝料
後遺障害の等級が正しく認定され、適切な金額が提示されているかの確認が必要です。
3-2-5 逸失利益
後遺障害によって将来的に失われる収入分が適切に計算されているかという点が重要です。
3-2-6 物損
車の修理費用、代車費用、評価損などが含まれているかについて確認が必要です。
3-2-7 後遺障害が残った場合は要注意
特に、後遺障害が残った場合、慰謝料や逸失利益の計算は非常に複雑になります。保険会社が提示する後遺障害の等級が妥当なものか、弁護士の意見を聞くことが望ましいでしょう。
3-3 金額の妥当性
最も重要なのは、示談金総額の妥当性です。先に述べたとおり、保険会社が提示する金額は「任意保険基準」に基づいているため、被害者自身が計算する「弁護士基準」とは大きな差があります。保険会社の提示額を鵜呑みにせず、弁護士に依頼した場合の想定額と比較検討することが欠かせません。
4 保険会社から示談書が届いた段階で、なぜ弁護士に相談すべきなのか?
示談書が届いた段階は、まさに弁護士に相談すべきタイミングです。その理由は以下のとおりです。
4-1 専門知識による適切な判断
交通事故の損害賠償は、専門的な法律知識がなければ適切な判断が難しい分野です。特に、後遺障害の等級認定や逸失利益の計算は複雑であり、一般の人が正確に理解することは困難です。弁護士は、過去の裁判例や専門的な計算方法に基づき、被害者が受け取るべき適正な賠償額を算出することができます。
4-2 交渉の代行
先ほども述べたとおり、一度示談書にサインしてしまうと、原則として後から追加請求はできません。しかし、示談書にサインする前であれば、弁護士が保険会社との交渉を代理で行い、増額を求めることが可能です。
弁護士が交渉を行うことで、保険会社は「弁護士基準」での支払いを検討せざるを得なくなるため、示談金の増額が期待できます。
4-3 精神的な負担の軽減
保険会社とのやり取りは、被害者にとって大きな精神的ストレスとなります。何度もかかってくる電話や、専門用語が並ぶ書類の確認は、ただでさえ怪我でつらい状況の中で、さらに大きな精神的負担となるでしょう。
弁護士に依頼すれば、こうした交渉の一切を任せることができ、被害者は治療に専念することができます。
4-4 「弁護士特約」があれば費用倒れの心配が少ない
「弁護士費用が高いのではないか?」と心配する人も少なくありませんが、多くの自動車保険には「弁護士費用特約」が付帯しています。この特約を利用すれば、弁護士費用を保険会社が負担してくれるため、自己負担なく弁護士に依頼することが可能です。
4-5 示談に関するご相談は弁護士法人法律事務所DUONへ
保険会社から示談書が届いた際には、焦ってサインをしないようにしましょう。示談書の内容を十分に理解し、特に過失割合や示談金の額が適正かどうかを慎重に検討することが重要です。
もし、少しでも疑問や不安を感じたら、すぐに交通事故に詳しい弁護士に相談しましょう。弁護士は、被害者の味方となり、適正な賠償額を獲得するために尽力してくれます。示談書にサインする前に相談すれば、後悔のない解決へとつながります。
弁護士法人法律事務所DUONは、交通事故の示談交渉に関する実績が豊富です。また、交通事故に関する法律相談は初回無料となっております。
保険会社から提示された示談書に疑問を持ったら、どうぞお早めにご相談ください。