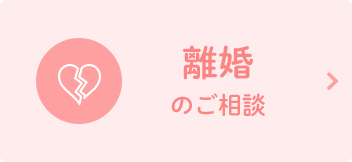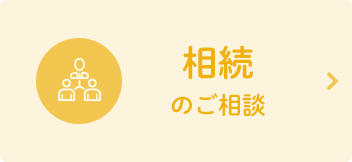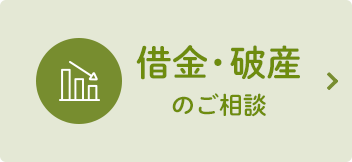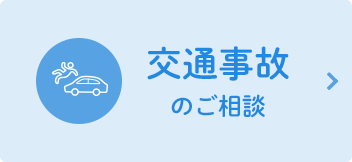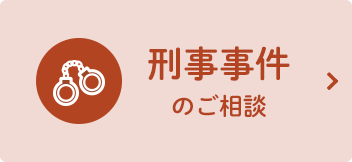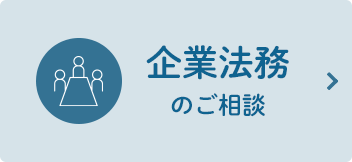後遺障害等級とは?後遺障害等級認定の基本を理解しよう
交通事故や労働災害などで大きなケガを負った場合、治療を続けても完全に元の状態に回復できないことがあります。視力や聴力の低下、手足の機能障害、神経症状の残存などが、将来にわたって症状が続く場合、それらを「後遺障害」と呼びます。
この後遺障害が一定の基準を満たすと、損害賠償や保険金の支払いにおいて「後遺障害等級」が認定されます。
後遺障害等級は、将来の生活に直結する重要な制度です。認定された等級によって、受け取れる損害賠償額や保険金額が大きく変わるため、制度を正しく理解し、適切な対応をとることが不可欠です。
そこで、今回は、後遺障害等級の基本について解説します。
1 後遺障害と後遺障害等級認定
最初に後遺障害とは何かということと、後遺障害等級の概要について解説します。
1-1 後遺障害とは何か
後遺障害とは、事故や病気の治療を行っても改善が見込めず、身体に一定の障害や機能の制限が残ってしまった状態を指します。
たとえば、以下のようなケースが後遺障害に該当することがあります。
- 視力が一定程度低下し、運転や細かい作業に支障がある
- 手足の可動域が狭まり、日常動作や仕事に制限がある
- 神経障害により慢性的な痛みやしびれが残る
- 顔や首に目立つ傷跡や変形が残る(醜状障害)
こうした障害の程度を数値化・類型化したものが後遺障害等級です。
等級は1級から14級まであり、数字が小さいほど重度の障害を意味します。
1-2 後遺障害等級の概要(自賠責保険基準)
後遺障害等級は、以下に示す障害の程度に応じて分けられるものです。
- 1級:常に介護が必要な状態(例:四肢麻痺、植物状態など)
- 2級:随時介護が必要な状態、または重度の視力・聴力障害
- 3〜7級:職業や日常生活に重大な制限を及ぼす障害(例:片腕の全廃、 片目失明+もう一方の視力低下など)
- 8〜14級:比較的軽度だが、一定の生活・仕事制限を伴う障害(例:関節可動域の一部制限、醜状障害、指の一部欠損など)
同じ等級でも障害の種類や部位によって細かい項目が設けられています。
2 後遺障害等級認定の仕組みと流れ
後遺障害等級認定は、主に自賠責保険制度に基づいて行われます。交通事故の場合、加害者が加入している自賠責保険に対し、被害者が申請します。
認定までの基本的な流れは以下のとおりとなります。
2-1 治療の終了(症状固定)
医師が「これ以上治療をしても大きな改善は見込めない」と判断する時点を症状固定といいます。症状固定後は、治療費の賠償は原則打ち切られ、後遺障害の有無を判断する段階に入ります。
2-2 後遺障害診断書の作成
主治医に「後遺障害診断書」を作成してもらいます。症状や検査結果、日常生活への影響が詳しく記載され、等級判断の重要資料となります。
2-3 申請方法の選択
申請方法には、事前認定方式と被害者請求方式の2つがあります。
事前認定方式は、加害者側の任意保険会社を通じて申請する方式です。一方、被害者請求方式は、被害者が直接自賠責保険に申請する方式で、必要書類を自分で揃える必要があります。
2-4 自賠責保険調査事務所による審査
自賠責保険調査事務所とは、正式名称を「公益財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構 調査事務所」といいます。交通事故で被害者が自賠責保険に請求をした際に、その請求内容が保険金支払いの条件を満たしているかどうかを中立的に調査・判定する機関です。
自賠責保険調査事務所では、医療記録や診断書をもとに、後遺障害等級が判断されます。必要に応じて追加の資料提出や面談が求められることもあります。
2-5 結果の通知
認定結果は書面で通知されます。不服がある場合は異議申立てをすることができます。異議申立ては、認定結果を通知してきた自賠責保険会社に対して行います。
保険会社が再び調査事務所に資料を送り、再調査を依頼する仕組みになっています。
異議申立てに際しては、新しい医学的証拠や資料を添えることが非常に重要です。
3 等級認定されるためのポイントと注意点
後遺障害等級は、単なる症状の申告だけでは認められません。医学的証拠と事故との因果関係が重要です。以下に等級認定されるためのポイントや注意点について解説します。
3-1 症状固定までの通院記録を継続する
通院間隔が空くと「症状が軽い」と判断されやすくなるので、注意が必要です。
3-2 診断書の記載を具体的に
たとえば、「腕が上がらない」ではなく「肩関節の可動域が90度まで」など、数値や検査所見を明記してもらうようにすることで、有利に等級認定されやすくなります。
3-3 画像検査の活用
MR画像やCT画像で異常が確認できる場合、客観的証拠となります。
3-4 事故との因果関係の立証
事故後すぐに医療機関を受診し、診断名を明確にしておくことが重要です。
4 後遺障害等級が認定されるメリット・デメリット
後遺障害等級を認定されることにより、どのようなメリットやデメリットが生じるでしょうか。
4-1 メリット
メリットとしては以下のものが挙げられます。
4-1-1 損害賠償額が増える
後遺障害慰謝料や逸失利益が加算されます。等級が重いほど金額も大きくなります。
4-1-2 保険金の受給
後遺障害等級が認定されると、障害の程度に応じて自賠責保険・任意保険・労災保険から給付を受けられるようになります。
これらの保険金は、それぞれの制度で独立して支給されるため、条件を満たせば複数の保険から受給することが可能です。結果として、将来の生活費や医療費、介護費の大きな支えとなります。
4-1-3 生活再建の資金確保
後遺障害が認定されると、将来にわたって必要となる生活費や環境整備の費用を、損害賠償や保険金でまかなうことができます。たとえば、介護サービスの利用費用、車いすや義手・義足などの補装具購入費、手すり設置や段差解消といった住宅改修費などが挙げられます。
認定された損害賠償金や保険金を、これらの費用に充てることで、できる限り事故前に近い生活環境を取り戻し、安心して暮らせるようにすることが可能になります。
4-2 デメリット
一方、デメリットには以下のようなものがあります。
4-2-1 認定までに時間がかかる
申請から結果まで数か月〜半年以上かかることもあります。
4-2-2 症状固定後の治療費は自己負担
原則として症状固定後の治療費は、賠償対象外となり、保険から受け取ることができなくなります。
4-2-3 希望した等級にならない可能性
医学的基準を満たさなければ、実際の不自由さがあっても希望した等級に認定されないことがあります。
5 弁護士に相談するタイミング
後遺障害等級認定にあたっては、医学と法律の両面からの知識が求められます。そのため、以下の段階で弁護士に相談することを検討しましょう。
- 症状固定の前:診断書記載内容のアドバイスを受ける
- 申請準備時:必要な検査や資料の確認をする
- 認定結果に不満があるとき:異議申立ての戦略立案をしてもらう
- 高額な逸失利益が見込まれるケース:将来の収入減を正しく評価しても らう
6 まとめ
後遺障害等級認定は、事故後の人生設計を左右する重要な手続きです。
正しい知識を持ち、症状や生活への影響を適切に記録・証明することで、適正な認定を受ける可能性が高まります。
不安や疑問がある場合は、早めに交通事故や労災に詳しい弁護士へ相談し、将来の生活の安定をはかることが必要です。
当事務所は、後遺障害等級認定に深い知見を持っており、実績も豊富です。
交通事故などに遭い、後遺障害等級認定の申請をご検討されている方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。