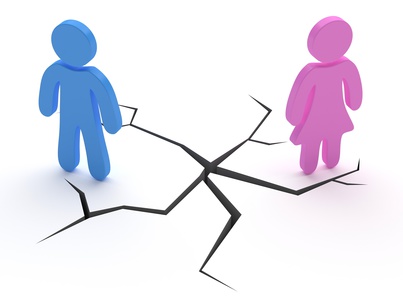【無料相談受付中】法律事務所DUON は法律相談に習熟した弁護士チームです。

簡単予約
DUON なら電話で毎日24時まで予約できます。
無料法律相談のご予約は、フリーダイヤルからお申し込み頂くと、ご予約日の設定まで完了しますのでスムーズです。
電話で毎日24 時まで予約できます。
![]() 0120-074-019
0120-074-019
相談予約受付時間:平日・土日祝日6 時~24 時
※お取り扱いできない案件がございますので予めご了承ください。
法律相談をご検討の方はお読みください。
当事務所の特徴・強み

初回相談無料

相談予約しやすい
毎日24時まで電話で予約可

抜群の法律相談実績
相談実績7,000件以上
(~2023年4月累計実績)
(~2023年4月累計実績)

明確な料金提示

秘密厳守
完全予約制